
アメリカ人にとっても最後の未知・テキサスの辺境音楽
レコード・ジャングル 中村政利
「テキサス人はテキサスがアメリカよりも広いと思っている」というジョークがある。テキサス人を象徴する今の大統領の無知と鈍感と傲慢を思い起こせば、そんなジョークもあながち的をはずれたものではない気がする。だが、現代の情報社会とグローバルな価値観から一歩遅れた地域だからこそ、そこには原風景としてのアメリカの美意識が強く残っており、多くのアメリカ人にとって郷愁の沸く土地なのだ。
それだけではない、テキサスは19世紀初頭からフロンティアの最前線として白人がメキシコ領内に侵攻し、ついに1845年の米墨戦争でメキシコから奪い取った土地だ。テキサス州内には今も色濃くメキシコの文化が残るどころか発展し、その地に住むメキシコ人たちは自分たちをメキシコ北部に住む「ノルテーニョ(北部人)」と呼ぶくらいなのだ。リオ・グランデ川を越えたメキシコからの不法移民はひきもきらないし、多くのノルテーニョたちは両国にまたがって親戚、縁者を持っている。
白人がメキシコ領に侵攻したのは黒人奴隷を酷使する綿花栽培の畑を求めてであった。連れてこられた多数の黒人たちも乾燥したテキサスの地で独自の文化を発達させていく。その後、この地で石油が発見され、衰退する綿花産業に代わって、かれらの多くが石油産業の労働者として都市生活者になるにしたがってさまざまな都市黒人音楽もこの地に発展することとなった。
「ローン・スター・カントリー(ひとつ星の国)」と自らを誇るこの大きな州にはこうやって、白人、メキシコ人、黒人の文化が散在し、混合し、あるいは葛藤しあって、独特の果実を実らせているのだ。
Lyle Lovett “ Live In Texas” (Curb/MCA MCAD
11964) \2310 
3つ折のジャケットには総勢16名のミュージシャンやスタッフのポートレイトが、そして、その白人、黒人、メキシコ系が入り混じった顔ぶれから、ここテキサスが3つのエスニック文化が混在した土地であることが窺える。リーダーのライル・ラヴェットは表紙右上のうらなりひょうたん顔の白人。美女ジュリア・ロバーツを妻として口説き落としたB級俳優としても知られる。そして彼がまとめる音楽は、ヒューストン・ジャンプと呼ばれる激しい50年代風のR&Bと40年代のウェスタン・スウィングとが結合しファンクの洗礼を受けたかのようなビッグ・バンドによるジャジーなバラードとダンス音楽。ひょうひょうとして憂いのあるかれの歌声に独特のソウルを感じるのは僕だけではないだろう。カントリー音楽の括りで語られることが多いけど、Tボーン・ウォーカーやゲイトマウス・ブラウンなどのブルース好きにこそ聞いて欲しい黒くてゴージャスなジャンプ音楽の側面もあり、白人音楽と黒人音楽の伝統がもっとも理想的に融合し発展したような美しさを感じさせる95年のライヴ録音。フランシーン・リードやスイート・ピー・アトキンソンの参加はソウル・ファンにも嬉しいはず。
Lydia Mendoza “First Queen Of Tejano Music”
(Arhoolie392) \2310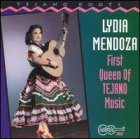
ブルースやフォーク音楽を紹介するレコード会社として知られるアーフーリー社の社長クリス・ストラックウィッツは本当はテキサス音楽を紹介したくって会社を設立したのだと聞いたことがある。そんな彼にとっての女王は間違いなくこのリディア・メンドーサだろう。貧しいメキシコ移民の娘として、精一杯に生きている激情を畳み込むようなスペイン語で歌い上げる。クリスが製作したテキサス音楽の紹介ビデオ“Chulas Fronteras”のサントラLPなかで「冷たい男」というオハコを歌う老境に達したリディアのうたのコクを通り越したアクの強さったら無かった。クリスは1920年代から1980年代までの彼女の録音を何枚ものアルバムで紹介しているが、もっとも円熟期である50年代から60年代前半にかけてのものをこのCDで聞くことができる。バックの演奏も素晴らしいのだが、それに輪をかけて緩急自在の余裕のこぶし回しでリードするリディアの歌唱の力のあることよ。「うた」のちからに改めて気づかされる名歌手の名アルバムだ。20年後の八代亜紀や天童よしみは同じように酔わせてくれるのだろうか。
Freddy Fender “ The Best Of Freddy Fender” (MCA
MCAD-11464) \1890
テキサスの出稼ぎ労務者のセンチメントを歌わせたらこの人にかなうものは無いというのが、このフレディー・フェンダーだ。75年に録音された代表曲である”Before The Next Teardrop Falls”は単純に甘口のラブバラードとして聞くことも可能だ。だが僕には別の情景が目に浮かぶ。LAやラス・ヴェガスへ季節労働者として旅たつ男が家族や恋人に車窓越しに告げねばならないウソの約束。「どんなに離れていようとも、キミが涙の一滴を落とす前に、ボクは必ずソバにいくからね」。たとえウソだと分かっていても、旅たつ者も残される者も、その言葉をよりどころに数ヶ月を耐えねばならないという悲哀を思うと、歌とそのツクリの軽薄さが逆にリアルにこころをかきむしるものとなる。チャールズ・ブラウンの”Please Come Home For Christmas”もフレディーの手にかかれば、「せめてクリスマスには家に帰って欲しい」という愛する者と別離した出稼ぎ労務者のかなわぬ願いとなって聞こえるのだ。あるビデオの中で下積み時代を思い出してフレディーは語っている。「俺が歌ってきたのはテックスメックス(メキシコ系テキサス人)たちの感情が爆発するような修羅場さ。そこでは、ガードマンが入場者を必ずボディー・チェックし、銃を持ってない奴には銃を貸してくれるようなところなんだ」。こんな冗談のウソくささが逆にリアリティを感じさせるというのは彼のうたと同じだ。
Matthew Robinson “Matthew Robinson & The Texas Blues Band” (Dialtone DT0006) \2499
「緩急」すなわち緊張と緩和ということがブルースという音楽の美意識の中心にあると思う。多くの白人ブルースマンが物足りないのは、その緩急の対比でダイナミックに曲を構成することができないからだ。クラプトンのスロウハンドじゃあイケない理由もまさにここにある。このマシュー・ロビンソンはそんな緩急の妙をこれでもかというくらい感じさせるオースティンのゲットーたたき上げのブルースマンだ。すでにキャリア40年というのに2枚のアルバムしか出ていないし国内盤で紹介されたことももちろんない。だが、たたき上げにはたたき上げなりの存在感がある。目を閉じれば、黒人街の小さなクラブでスポットライトひとつを浴びてステージに立つマシューの姿が目に浮かぶ。歌い、語り、叫び、うなるその言葉のすべてが、そしてみずからの言葉に呼応してかきならすギターの響きのすべてが、その場に居合わせたこころに傷をもつ中年男女の聴衆すべての感情の起伏にシンクロして共鳴する。身をかたくし、こぶしを握り締めて、あるものは身体の中で、そしてあるものは口に出して気持ちを吐き出さずにはいられない。「イェーッ!」。このカタルシスがあるからこそ、ブルースが好きでよかったと、黒人音楽が好きでよかったと思える自分が嬉しい。
Hot Club Of Cowtown “Continental Stomp” (Buffalo BUF-118)
\2500
新しい感覚のカントリー音楽(オルタナ・カントリー)の中心地として脚光を浴びるオースティンで、シーンの原動力となって注目を集めるウェスタン・スウィング・トリオがこのホット・クラブ・オヴ・カウタウンだ。このグループは30,40年代にテキサスで盛んであったウェスタン・スウィングを再現するだけのトリオでは決して無い。グループ名を同じ時代にパリで活躍していたジプシー・スウィングの巨人ジャンゴ・ラインハルトのバンドから採っていることからも分かるようにクロスオーバーな志向を強く持った3人組なのだ。メンバーはそれぞれ、クラシック、ジャズ、ロック、ロカビリー、ブルースなどさまざまな音楽遍歴の果てにテキサスのルーツ音楽へとたどり着いた、ギター、フィドル、そしてウッドベースのつわものたち。古い曲に現代的で斬新な感覚を加味しスピード感あふれるアレンジで蘇らせるセンスと技量には驚嘆するしかない。このアルバムは昨年発表されたグループはじめてのライブ・アルバム。3人という最小ユニットから生み出される丁々発止の緊張感と息付く暇も無いようなドライヴ感は「もっとも伝統的なものを土台にしてもっとも創造的な作品が生み出される」というポピュラー音楽の定理を再確認させる魅力にあふれている。この10月には2年ぶりの来日公演を果たすこのグループがさらに成長を遂げていることを期待して、このアルバムで予習しておきたい。